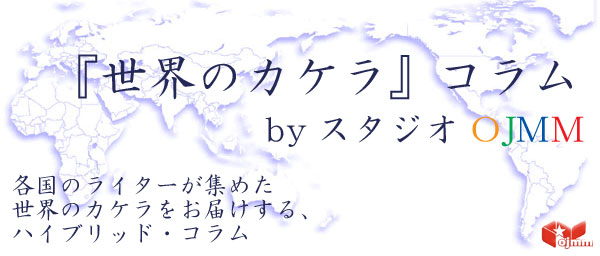|
連載 第1回 2006年4月号
ここにあります、世界のカケラ! 〜執筆者・滞在都市の紹介〜
今回の企画のため、スタジオOJMMがツテをたどって声をかけ、世界各地で8名のライターが決起しました。しかし、世界のカケラを拾い上げてくるという使命を課せられたライターたちもまた、世界のカケラなのです。まず初回は、コラム執筆者たち、そしてその滞在都市の素顔を、少しお見せします。世界のカケラが、ここにあります!
|
|
|
オリンピックの記憶も新しいイタリア北部の工業都市トリノ。僕はあの街で生まれました。首を据わらせる余裕すら与えられないまま生誕の地を後にした僕は、琵琶湖畔に落ち着きます。仏教系の保育園で幼少を過ごし、精進料理をさらりと食卓に乗せるイタリア人の母に日本語で育てられた僕は、高校卒業時点で話せるイタリア語がボン・ジョルノとチャオだけという、混血児としては異常な事態を迎えてしまいました。相貌と口にする関西弁との著しい乖離という由々しき問題に対処するべく、僕は単身大阪外国語大学に乗り込みました。それから9年。今もってイタリアとの接触に飽き足らない僕は、ローマ第3大学で博士論文執筆の準備をしていることになっています。しかし、実際には余計なことに余念がありません。例えば、大阪ドーナッツクラブというグループを主宰して、イタリアの知られざる映画・演劇・文学を日本に紹介する活動を行っています。「イタリアとはおよそ縁もゆかりもなさそうなグループ名だね」と人によく言われるのですが、まぁ、それはそれとして。さて次回からは、こんな僕がローマで採集した選りすぐりのカケラを丹念に磨き上げて、皆さんにお届けします。 |

野村雅夫
イタリア
ローマ |
|

松野早恵
オランダ
ユトレヒト |
晴れた土曜日の午後、アムステルダム国立美術館。展示室の一角で、ガイドが日本人来館者に語りかける。「さあ、ご覧ください。フェルメールの『青衣の女』です。穏やかで、透き通った光が絵の左側から差し込んでいます。私たちの眼差しは、光を追って、左から右へと導かれていきます。」通訳を務めつつ、私も作品を見つめる。
アムステルダムに留学して、もうすぐ3年。最近は、17世紀の室内画に描かれたオランダの光と空気も、身近なものとして目に映る。フェルメールの時代から400年を経た今も、オランダの街は、この「醒めてはいるけれど、決して冷淡ではない」光に照らされている。そして、いつも不思議ではあるのだけれど、アムステルダムには、居場所を模索する外国人がさりげなく風景の中に溶け込めるような、そんな開放的な雰囲気がある。
これまでの留学生活を思い出すと、地図を片手に、建物を探して街を歩き回る自分の姿が浮かぶ。美術史から建築・都市史に転向し、試行錯誤の毎日。少しずつ時間をかけて、小さな通り、運河の一つ一つに、「場所」の過去と現在が丁寧に織り込まれた「物語」があることを学んできた。その一端をこのコラムで紹介できることを、とても楽しみにしている。
[撮影:Dafne Arlman]
|
|
|
|
高校2年生の時に、新聞で「アフリカのスーダンでは子どもの奴隷が未だ存在し、人身売買というものが平然と行われている」という記事を読み、強くアフリカと子どもの人身売買に興味を持つことになる。現在、人身売買が盛んに行われている西アフリカ・ガーナ共和国へ大学院留学中。研究テーマは「ガーナ共和国ボルタ州トング地域における里子制度と子どもの人身売買の社会相関関係」。
アフリカと言うと、野生動物や、槍を持ち腰に布を巻いて生活している人々を想像されがちだが、私の住むアクラはビルやマンション、ホテルにプール、フレンチレストランまである都会。もちろん野生動物が道をうろついているということはない。ただ、そういった都会の中にも大きなスラム地区がいくつもあり、道には物乞いや物売りの少年少女が溢れている。混沌とした都市ではあるが、人々はいたって陽気で人なつっこい。どれだけ貧しくてもそれを困難と思わず、家族や近所で助け合いながらたくましく楽しく生きている。
ここでは、歴史的にも地理的にも遠いアフリカ、ガーナという国や人々の暮らしといった、国連の報告でも知りえない現状を伝えていきたい。ただ「貧しい国」「文明のない国」というステレオタイプ的なイメージだけでなく、より具体的に多くの人にアフリカを近くに感じてもらえればと思う。 |

澤恵子
ガーナ
アクラ |
|

ユゴさや香
ドイツ
フランクフルト |
留学経験も海外生活への憧れもなかった私が、ドイツに住み始めて早3年。思い起こせば全ての始まりは一本の電話からだった。
「日本語専攻のフランス人に、日本語を教えてあげる代わりに英語を習ってみない?」なぜフランス人に英語?心理学専攻の私がなぜ日本語を教える?と疑問に思いつつ気まぐれに引き受ける。まさかそのフランス人が夫になろうとは!C'est
la vie.
日本語が堪能な夫のおかげで、全くフランス語が話せなかった私。折角フランス語を学ぶ動機があるのだからと、気軽な気持ちで渡仏。10ヵ月後。やっと生活にも慣れてきたある日、転職希望の夫が、とある求人に応募。履歴書送付後、勤務地がドイツだと知るが時すでに遅し。採用決定。
そんなわけで気が付けば何のゆかりもないドイツでドイツ語を学び、去年は出産まで経験。生活にも慣れ、現在は雑誌に記事を書く傍ら育児に追われる毎日。暇を見つけては近郊の町を訪れ、その歴史や文化に触れ、すっかりドイツを満喫している。
|
|
|
|
大学入学から丸10年になる。18歳の時、10年後も学生であり続け、ましてやインドに留学するとは想像していなかった。「インドに興味を持ったきっかけは?」とよく訊かれるが、学部生時代のインドゼミ旅行か、高校生の頃読んだE.M.フォースターの『インドへの道』か。一度の衝撃的体験がきっかけというより、大小さまざまな機会がじわじわ効いてきて、私をインドに深く関わらせている気がする。
ところで、夏から1年間生活するムンバイー(旧名ボンベイ)は、インド一の大都会である。近年インドでは西洋的価値観が急速に広がり、ムンバイカル(=ムンバイっ子)は最も強くその洗礼を受けた今ドキな人々である。ムンバイーには、スタバのようなカフェもウォルマートもある一方で、チャーイの屋台も至るところで健在である。この連載では、このように旧来の伝統と新しい文化様式が対立・共存する、現在のムンバイーだからこそ見えてくる、インド的あるいは普遍的な事象について切り取っていけたらと思う。 |

豊山亜希
インド
ムンバイー
(旧名ボンベイ)
|
|

寺西悦子
オーストラリア
ブリスベン |
G'day, mate! はてしなく続く青い空、整えられた芝生、素敵な川沿いの町並み、鳥たちの鳴き声−オーストラリアに来て4ヶ月。東南アジア(ラオス・カンボジア)での国際協力関係の仕事から、学業の道に。ゴールドコーストまで車で1時間のところに位置するブリスベンにあるクイーンズランド大学大学院の修士課程で国際関係(平和・紛争解決学専攻)の勉強をしています。世界で起こっていることを、理論だけで解釈しするのではなく、身近なもの、自分のまわりのものに照らし合わせて、いかにクリエイティブな活動ができるか模索中。
息抜きに、サーフィンをしようとはりきって来たものの、授業が始まるや、ブリスベンの街中に行く余裕すらない現実。あまりにもまぶしい太陽とサーフボードを横目に、波に乗っている姿を想像している日々です。
まさに『世界のカケラ』、世界各地からの人々が住む国から、日常、学生生活を通して、新しい発見を届けていけたらと思っています。 |
|
|
|
I'm 29 years old, a misplaced scientist rounding the outskirts of a non-existent
career, and I have penchants for photography, bodybuilding, テニス, taking
every kind of physical and mental health サプリメント known to man, random learning,
引きこもり, and spending more than I can afford on everything that takes my
fancy.
I like "doing things the hard way". Which is to say, I wanted
to learn a language, so I chose 日本語 because I heard that it was difficult
(I knew nothing about Japan at the time), and then I ultimately chose to
come to 大阪 because I heard the 大阪弁 was difficult to understand. Of course,
I also heard that it was the best place in Japan for 食べ物, ユーモア and 親しみやすさ
overall. Most of the natives also claim it to be the best in every other
conceivable regard, and I generally believe them, especially if they are
referring to "urban decay", the near omnipresence of which lends
a great deal of artistic validity to what might otherwise be a sprawling
grey ugly hulk of a city. I do love it though. |

Simon Nettle
日本
大阪 |
|
ご感想、ご批判、などは、お気軽にコチラまで。
牧尾晴喜 harukimakio*aol.com
*を@に変えてください。
|
|